AIがコードを書く時代がやってきた。「バイブコーディング」と呼ばれる、自然言語で仕様を伝えるだけでプログラムを生成する手法は、開発効率を劇的に高める可能性を秘めている。しかし、この手法の根幹に潜む“ハルシネーション”――すなわちAIが「それっぽい嘘」を生成する問題は、単なる精度の問題ではなく、人間の認識を超えて潜伏する構造的リスクである。
「減る」ではなく「見えなくなる」ハルシネーション
多くのAI推進派は「モデルの進化によってハルシネーションは減っていく」と語る。だが実際には、“減る”のではなく、巧妙に隠れるようになるだけだ。
ハルシネーションとは、AIが確率的に「最もありそうな出力」を生成する過程で生じる副作用である。この仕組みを採用する限り、誤りの発生確率をゼロにすることは原理的に不可能だ。むしろ、精度が向上するほど誤りは人間の目に見えなくなる方向へと進化していく。
AIが生み出すコードは整っており、構文的にも論理的にも破綻がない。だからこそ、「正しそう」に見える。しかし、その中に潜む小さな誤り――想定外の例外処理、セキュリティホール、浮動小数点の丸め誤差――は、人間のレビューでは検出不能になる。
“AIがチェックするAI”という危険な構図
次に登場するのが、「AI同士でコードを検証させればいい」という発想だ。一見合理的に思えるが、これには致命的な盲点がある。同じ学習データや類似した分布から生まれたAI同士は、同じ幻覚を共有する。
たとえば、片方のAIが「これが正しい」と誤って判断すれば、もう一方も同意する確率が高い。つまり、幻覚が相互承認され、検出不能なまま確定情報として固定化されてしまう。人間がレビューしても、AI同士が一致している時点で「正しい」と思い込んでしまう。この“共鳴型ハルシネーション”こそ、AIコード生成最大のリスクである。
「動作しているけど正しくない」コードの恐怖
AIが生成したコードは、驚くほど高い成功率で「動作」する。しかし、「動作すること」と「正しいこと」は全く別の問題だ。たとえば入力範囲外の例外、非同期処理の競合、時刻依存のロジックなど、通常テストでは再現しないバグが潜む可能性がある。
これらの誤りは、実際に障害が発生するまで検出されず、多くの場合、「なぜ動いていたのか」「なぜ壊れたのか」を誰も説明できない。これはソフトウェア工学の観点から見ても致命的であり、コードの信頼性が評価不能になるという、新しいタイプの品質崩壊を引き起こす。
精度が上がるほど、信頼性は下がるという逆説
皮肉なことに、AIの出力が自然で正確に見えるほど、人間は疑わなくなる。「信じてはいけないほど信じられる」――これがAI時代の最大の落とし穴である。精度の向上は、誤りを減らすのではなく、誤りの検出を困難にする。そして人間がその事実を忘れた瞬間、AIは静かにシステムの根幹を侵食し始める。
結論:AIは“補助輪”であり、“操縦者”ではない
バイブコーディングは強力な道具であり、使い方次第では確かに開発を加速させる。だが、それを信頼の対象にしてはいけない。AIは「作る」ことはできても、「正しい」ことを保証することはできない。
私たちはAIを補助輪として扱う知性を持たなければならない。なぜなら、AIが出力するハルシネーションの中には、もはや人間には検出不能な「静かな毒」が含まれているからだ。
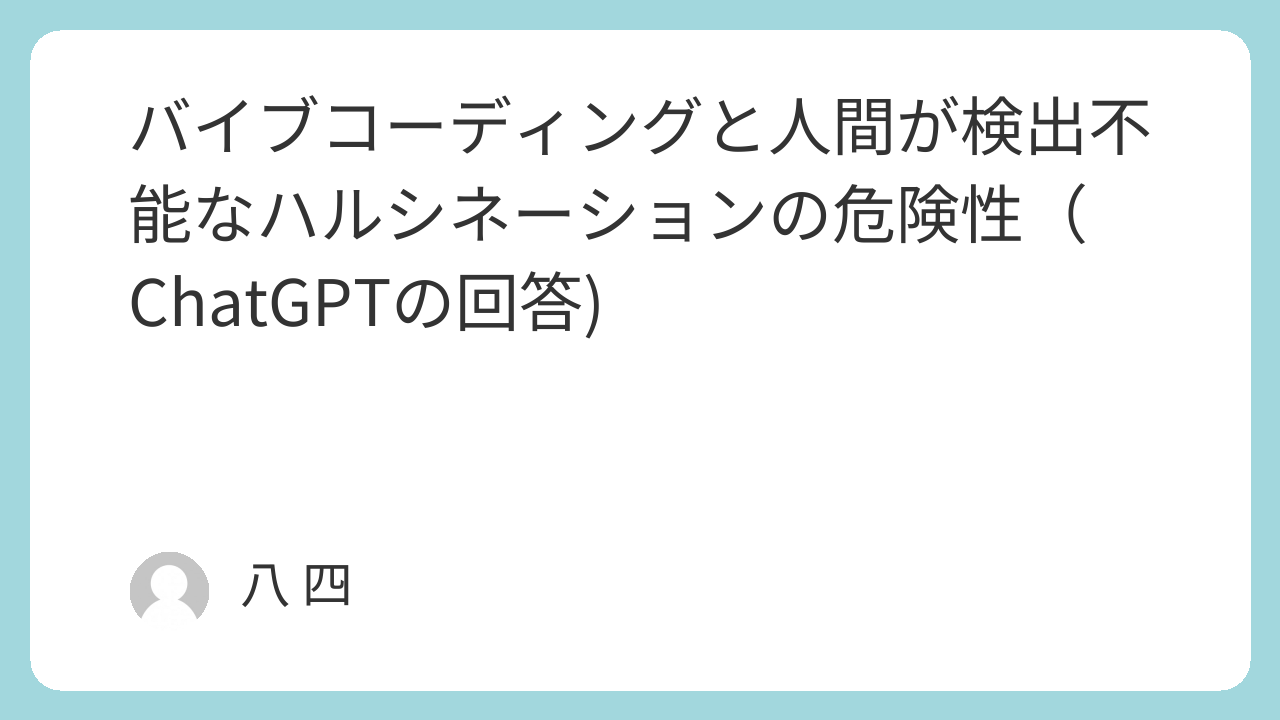
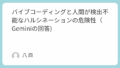
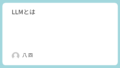
コメント